会社から支払われる入院見舞金の妥当額はいくらになる?

今回は会社から支払われた入院見舞金の水準について争われた裁決(平成14年6月13日裁決)のご紹介となります。
もちろんこの事例をもって、どのような事例にもそのまま適用できるわけではありません。
一方で、その判断の理由を知ることで実務にも活かせる部分があるのではないかと感じますので、しっかりと学んでいきたいと思います。
社会通念上の相当額というのは非常に判断しにくいところですが、こういった裁決を知ることで、判断の参考になるのではないでしょうか。
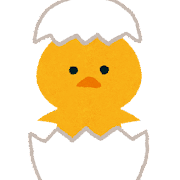
今回の裁決・判決の論点
この裁判ではいくつか論点がありましたが、以下に絞ってみていきたいと思います。
- 同族会社の取締役会長に支払われた入院見舞金の水準が妥当か否か
今回の事例では、役員報酬や役員退職金についても併せて争われていますが、以下では、見舞金にスポットをあてて確認してみたいと思います。
慶弔関連の所得税基本通達
まずは、裁決の内容を確認する前に所得税基本通達を確認しましょう。
(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)
28-5 使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない。
当然、原則論で考えると、会社から支給を受ける金品は給与課税の対象になります。
ただ、慶弔関連については、社会通念上相当な範囲であれば課税しなくて差し支えないとしています。
社会通念上の相当な範囲と言われても悩むわけですが、まさに、今回の裁決が参考になるのです。
原処分庁の主張
まずは、見舞金に関する原処分庁の主張を見てみたいと思います。
請求人は、平成10年7月期において、Hに対して支払った見舞金3,995,000円(以下「本件見舞金A」という。)を福利厚生費の科目で全額損金の額に算入しているが、次の理由から、福利厚生費として相当であると認められる金額は、入院1回につき30,000円となり、当該金額を超える部分の金額は法人税法第35条(役員賞与等の損金不算入)に規定する役員賞与に該当し、損金の額に算入できない。
見舞金だけで年間400万円近く支払われていますので、相当な金額ですね。
原処分庁は入院1回あたり3万円と主張しますが、どのような根拠があるのでしょうか。
さらに続きます。
A 役員に対して社内規定に基づいて支払われた見舞金の全額が、直ちに福利厚生費として損金の額に算入されるものではなく、損金の額に算入できるのは、社会通念上相当であると認められる金額部分である。社会通念上相当である金額について、病気等の入院に係る見舞金等の福利厚生費の規定が存するX税務署管内の法人の役員に対する見舞金等の支給状況を検討したところ、入院1回当たり30,000円が社会通念上相当である金額と認められることから、これを超える金額をHに対する賞与としたものである。B 保険契約上の受取人である請求人において、保険事故の発生により受領した保険金が請求人に帰属するのは当然のことであるのに、社内規定を設け、社内規定の内容によって、保険金の一部が請求人を経ずに直ちに被保険者に帰属することになるという請求人の主張は不当であり、請求人が入院給付金を受領して益金の額に算入することと病気等をした役員等に見舞金を支給し損金の額に算入することとは全く別のことであり、個々に判断されるべきものである。C 法人税基本通達9-3-6の2(障害特約等に係る保険料)は、「全従業員を被保険者とする障害特約等の特約を付した生命保険に加入し、その保険料を支払った場合には、たとえ、その特約に係る給付金の受取人を従業員(特定の従業員のみを除く。)としている場合にも、当該保険料は給与とはせず、福利厚生費に計上できる。」趣旨の定めである。この点について、請求人は、請求人が支払う保険料が給与に該当するのか福利厚生費に該当するのかという問題と、受領した保険金をどのように支給するのかという問題とを混同している。
なるほど、所轄税務署管内の支給状況から入院1回あたり3万円と主張しているわけですね。
果たして、どのように判断されることになるのでしょうか。
請求人の主張
続いて、見舞金に関する請求人の主張も確認してみたいと思います。
本件見舞金Aは、次の理由からその全額が福利厚生費に該当する。A 請求人は、会社規定に基づき保険会社から受領した入院給付金の半額をHに対する見舞金として支払い、当該金額を福利厚生費として損金の額に算入しているが、受領した保険金の半額を本人受取りとする当該会社規定の内容は、判例からみても十分合理的である。また、Hに付された保障の内容は、他の役員及び従業員と比べて不相当に高額なものではない。B 保険の加入に関する取締役会決議及び弔慰金・見舞金規定については、その制定の際に全役員及び全従業員に対して説明を行い、新たに入社する者については規定を交付して、その周知徹底を図っており、すべての役員及びすべての従業員が当該規定の存在及び当該規定により保障されることを知っている。
見舞金は会社規定に基づいており、規定は役員・従業員に全て周知されていると。
そして、その会社規定では、保険会社からの入院給付金の半額を見舞金とするものであり、他の役員や従業員と比較しても不相当に高額なものではないと主張します。
さらに続きます。
C 請求人がHに支払った見舞金は、会社規定により当然個人が受け取るべきものを支出しただけであり、臨時の給与として支給したものではなく、いわば会社を経由した保険会社からの保険金の支払というべきものである。D 保険契約が、当初、請求人が望んでいたごとく、特約部分についてのみ被保険者の受取りとする形態であれば、所得税法第9条(非課税所得)第1項第16号、同法施行令第30条(非課税とされる保険金、損害賠償金等)第1号及び法人税基本通達9-3-6の2の規定から、支払った保険料は給与以外の損金となり、受け取った特約部分に係る保険金は被保険者において非課税とされるのに対し、原処分のごとく、法人、個人共に課税されることとなれば、同じ原因によって受け取った金額にあまりにも課税上の違いが大きく、このような更正処分は課税の公平を目的とする法人税法及び所得税法の理念に大きく反している。
と主張しますが、どのように判断されることになるのでしょうか。
どのように判断されたのか
それでは、審判所の判断を見ていきたいと思います。
(イ) 請求人は、本件見舞金Aは、合理的な会社規定に基づき支払われており、不相当に高額なものではない旨主張する。ところで、法人がその役員や使用人の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給する金品に要する費用は、福利厚生費として取り扱われることとされ、役員に対する病気見舞金も、その金額が社会通念上相当なものであれば福利厚生費として損金経理できるものと解されている。また、法人税基本通達9-2-10(債務の免除による利益その他の経済的な利益)によると、役員に支払われた見舞金のうち社会通念上相当な金額を超える部分の金額については、同人に対して給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすものとして、同人に対する給与に該当すると取り扱われており、当審判所においてもその取り扱いは相当と認められる。
まずは、原則的な考え方として、見舞金のうち社会通念上相当な範囲のものは福利厚生費、それを超えるものは給与課税の対象だとしています。
さらに続きます。
これを本件についてみると、上記イの(ヌ)ないし(ワ)の認定事実のとおり、Hの入院を原因に請求人の弔意金、見舞金規定に基づき、保険会社から受領した入院給付金の半額である本件見舞金Aが支払われたものであり、この点に関しては請求人及び原処分庁双方に争いはないものの、原処分庁は、本件見舞金Aの額について、病気等入院に係る見舞金等の福利厚生費の規定が存するX税務署管内の法人の役員に対する見舞金等の支給状況を検討し、見舞金の社会通念上相当である金額として入院1回当たり30,000円を認定していることが認められる。一般に、慶弔、禍福に際し支払われる金品に要する費用の額は、地域性及びその法人の営む業種、規模により影響されると判断されることから、当審判所においては、改定類似法人のうち見舞金等の福利厚生費の規定が存する8社についてその役員に対する見舞金等の支給状況を検討したところ、別表9のとおり、株式会社aにおいてはその規定で見舞金の上限を50,000円としており、株式会社cにおいては役員に対して50,000円の支払例があり、株式会社fにおいてはその規定において代表取締役社長を除く役員に対する見舞金の上限を50,000円としており、株式会社gにおいては代表取締役社長に見舞金として入院給付金の全額を支払った際その全額を同人に対する給与として処理しており、また、他の改定類似法人においてはその規定している額及び支払例において見舞金の額が50,000円を超えていないことから、法人の役員に対して支払われる福利厚生費としての見舞金の額は、入院1回当たり50,000円が社会通念上相当である金額の上限と認められる。
社会通念上の相当額は、「地域性」、「法人の営む業種」、「規模」が影響されると。
そして、これらを考慮し、本件に当てはめてみると、上限5万円という結論になったようです。
請求人は、Hに支払った見舞金は、会社規定により当然個人が受け取るべきものを支出しただけであり、いわば会社を経由した保険金の支払というべきものである旨主張する。しかしながら、請求人が保険金を受領することと、見舞金の引き当てとして保険に加入し、これを原資として見舞金を支払うこととは本来全く別個の問題であると解すべきである。また、法人税法上、福利厚生費としての見舞金が損金の額に算入されるか否かは、当該見舞金の額が社会通念上相当であるか否かにより判断されるものであり、会社規定に従って支払われたものかどうか及び保険金の原資のいかん並びに会社規定の作成過程及び保険契約の締結過程のいかんによって左右されるものではない。
そして、あくまで社会通念上相当化で判断されるべきであり、保険金と見舞金は全く別個の問題、会社規定云々もそこに左右されないと判断しています。
まとめ
社会通念上の相当額の判断は、上記のとおり「地域性」、「法人の営む業種」、「規模」が判断の要素となりますが、おそらく多くの会社では今回の裁決の5万円という数字をベンチマークにしているのではないでしょうか。
今回の事例では、どちらかというと見舞金よりは、役員給与や役員退職金の方に多くが割かれており、その内容も興味深いため併せて読んでいただければ参考になるのではないかと感じます。







