贈与を受けた直後の譲渡に居住用3千万円控除は適用できるのか?

今回は贈与を受けた直後の譲渡に居住用3千万円控除が適用出来るのかついて争われた裁決(平成22年6月24日裁決)のご紹介となります。
もちろんこの事例をもって、どのような事例にもそのまま適用できるわけではありません。
一方で、その判断の理由を知ることで実務にも活かせる部分があるのではないかと感じます。
今回の事例では、税理士の提案で~という部分がしっかりと出てきていますので、そういう意味でも恐ろしい内容と言えます。
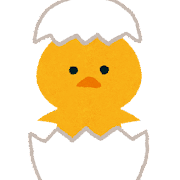
どんな内容だったのか
以下に事案の概要を抜粋します。
本件は、審査請求人(以下「請求人」という。)が譲渡した土地建物の譲渡所得について、原処分庁が、居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用はないとして所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行ったのに対し、請求人が、これらの処分は違法であるとしてその全部の取消しを求めた事案である。
ハ 請求人は、平成18年7月1日、本件A土地建物をDから贈与により取得した(以下、この贈与を「本件贈与」という。)。請求人は、平成18年7月18日、本件A土地建物について、同月1日贈与を原因として所有権移転登記を経由した。ニ 請求人及びDは、Fとの間で、平成18年7月19日、本件A土地建物及び本件B土地建物を65,000,000円で売買する旨の契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し、同日付で不動産売買契約書を作成した。なお、請求人及びDは、同日、Fから手付金10,000,000円を受領し、各5,000,000円を取得した。ホ 請求人は、平成19年3月12日、本件贈与に係る贈与税について、相続税法第21条の9《相続時精算課税の選択》第1項の規定に基づき、相続時精算課税制度を適用して平成18年分の贈与税の申告書を原処分庁に提出した。ヘ 請求人は、本件A土地建物について、別表4-1及び別表4-2のとおり、各変更登記等を経由した後、平成19年4月19日、Fとの間で、本件A土地建物を○○○○円で売買する旨の不動産売買契約書を作成するとともに、同人から残額○○○○円(Fが負担することとなった本件土地建物の平成19年度の固定資産税相当額200,000円のうち本件A土地建物に係るものとして請求人が取得した94,000円を含む金額)を受け取り、本件A土地建物の引渡しを行った。また、Dは、本件B土地建物について、別表4-1及び別表4-2のとおり、各変更登記等を経由した後、平成19年4月19日、Fとの間で、本件B土地建物を○○○○円で売買する旨の不動産売買契約書を作成するとともに、同人から残額○○○○円(Fが負担することとなった本件土地建物の平成19年度の固定資産税相当額200,000円のうち本件B土地建物に係るものとしてDが取得した106,000円を含む金額)を受け取り、本件B土地建物の引渡しを行った。なお、本件土地建物の売買については、上記ニのとおり、既に不動産売買契約書が作成されていたが、再度、不動産売買契約書を作成した理由は、平成18年7月19日付の不動産売買契約書には、本件A土地建物及び本件B土地建物の各売買価額が記載されていなかったこと、不動産表示が本件分筆後の表示となっていなかったこと並びに別表4-2の番号2欄に記載した○番3の2の居宅に附属する未登記の茶室が表示されていなかったことから、これらを明確にするためであった。ト 請求人は、平成20年3月10日、本件A土地建物の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算において、本件特例を適用する旨記載した平成19年分の所得税の確定申告書を原処分庁に提出した。
相続時精算課税制度を活用した贈与後に売買契約を締結し、譲渡したという流れですね。
そして、争点は、この譲渡した不動産が措置法第35条1項に規定する居住用のに供している家屋に該当するか否かということになります。
どのように判断されたのか(法令解釈)
まずは、法令解釈から見ていきましょう。
措置法第35条第1項の規定は、居住用財産を譲渡した場合には、譲渡者は再び居住用代替資産を取得する蓋然性が高いこと、通常の家屋であれば特別控除の額の範囲内で取得できるであろうとの配慮から、居住用財産の譲渡者が所得税の負担なくして普通程度の居住用代替資産を取得することを可能にする趣旨に出たものであり、この趣旨からすれば、譲渡者が当該家屋をその所有者として居住の用に供していたことを特別控除を認めるための要件とするものと解される。また、措置法第35条第1項が特別控除について連年の適用を認めず、3年間に一度の適用を認めたにとどまることにかんがみると、同項の適用を受けるためには、自らが所有する家屋について、真に所有者として居住する意思を持って、客観的にもある程度の期間継続して生活の拠点としていたことを要すると解すべきであり、その判定に当たっては、住居移転の経緯、居住の期間及び居住の態様等について総合考慮してこれを決すべきである。
上記の青色部分で、この規定の趣旨に言及します。
そして、赤色部分でこの規定の適用を受けるためには、「真に所有者として居住する意思を持ってある程度の期間継続して生活の拠点としていたこと」を要するとし、その判定にあたっては、総合的観点からの考慮の上で決すべきと言及しています。
どのように判断されたのか(事実認定)
まずは、贈与に至る状況としての審判所の判断となります。
上記ロの(ロ)から(ニ)までのとおり、請求人及びDは、平成18年1月、Hを介して、本件土地建物の譲渡についてJとの交渉を開始したこと、請求人及びDは、平成18年1月下旬以降、K税理士から、当時、請求人が居住していた本件A建物及びその敷地をDから贈与を受ければ、当該贈与に係る贈与税について相続時精算課税制度の適用を受けることができ、さらに、本件土地建物を譲渡した後、請求人の譲渡所得について本件特例の適用を受けることができる旨助言されたことからすれば、請求人及びDは、本件土地建物を一括して譲渡することを前提として、Dが請求人に本件A建物及びその敷地を贈与することを検討し始めたことが認められる。その後、上記ロの(ヘ)のとおり、平成18年5月にHを介して行われたDとJとの間の本件土地建物の譲渡に係る交渉はいったん中断されたものの、請求人が本件A建物及びその敷地を受贈した後の譲渡について本件特例の適用を受けるには、本件A建物の敷地を明らかにする必要があったため、請求人及びDは、本件A建物及びその敷地の贈与のための手続、すなわち、本件土地を分筆するための手続を進めたことが認められる。そして、①上記ロの(ト)のとおり、請求人及びDは、K税理士から、贈与税額及び譲渡所得に係る所得税額の試算内容の説明を受けながら、相続時精算課税に係る贈与税の控除の金額の上限額が25,000,000円であるため、請求人の受贈価額が25,000,000円を少し超えるようにして、本件土地の半分と請求人が居住している本件A建物を贈与することとしてはどうかという提案を受け、本件土地の面積が等分になるように分筆することを決定したこと、②本件土地は、別紙のとおり、本件A建物及び本件B建物の各敷地に対応する形で分筆されず、別表3-2の番号2の家屋番号○番3の2の建物が分筆後の別表3-1の番号5の土地にはみだすという状況となり、本件贈与後にDに残る本件B土地も不整形地となり、後日、別表3-2の番号2の家屋番号○番3の2の建物の附属建物として登記される茶室が本件A土地と本件B土地にまたがるという状況になり、請求人及びDは、本件A土地建物及び本件B土地建物を別々に譲渡することが困難になったことにかんがみれば、本件分筆は、本件贈与により請求人及びDがそれぞれ所有することとなる本件A土地建物及び本件B土地建物を一括して譲渡することを前提として、請求人が本件A土地建物の譲渡について、本件特例を適用して譲渡所得の申告をすることを目的としてなされたものと認めるのが相当である。
上記を読むと贈与・売却前からすでに一括譲渡の話が進んでおり、さらには、税理士の提案で贈与を進めていたということが分かります。そして、さらに、以下のように続きます。
上記(イ)で述べた本件贈与に至る事実関係の下、上記ロの(リ)及び(ヌ)のとおり、請求人及びDは、Jから中断前と同じ価額で本件土地建物の購入申込みを受け、平成18年6月26日までに、Dが、請求人と協議の上、Fの購入申込みを受諾する旨回答していることからすれば、請求人及びDとFとの間では、同日の時点では、譲渡物件、譲渡価額及び手付金の額も決定しており、同日以降は、売買契約の締結に向けた細部の取決めをするだけの状況になったものと認められるから、本件土地建物はFに譲渡されることが予定されていたものといえる。そして、請求人は、そのことを承知した上で本件A土地建物の贈与を受けたものと認められるから、請求人がDから本件A土地建物の贈与を受けて所有者となった平成18年7月1日以降において、請求人は、本件A建物を、所有者として居住する意思を持って居住の用に供していたものとは認められない。したがって、本件A建物は、措置法第35条第1項に規定する個人がその居住の用に供している家屋に該当しない。
請求人は、贈与前から10年以上にわたって今回の対象となる不動産に住んでいたとはいえ、贈与を受ける前の時点では既に譲渡をすることが予定されており、「所有者として居住する意思を持って居住の用に供したものとは認められない」、だから、3千万円控除は適用できないと判断されています。
まとめ
居住用の3千万円控除には所有期間や居住期間の定めはありませんが、この条文が言うところの居住というのはどういう意味なのかと言ことについて、言及されていますので非常に勉強になります。
もちろん、事例の個別性等もありますので、その辺りはご注意願います。
居住用の3千万円控除は、結構安易に考えられがちですが、色々と落とし穴もありますので、注意したいところです。また、今回の事例では、税理士の提案で~という部分があり、同業者としてはヒヤッとする部分なのではないでしょうか。









