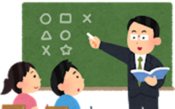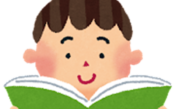税理士試験必勝法!?私の受験生時代のメモを復元しました

昔から名言を集めるのが好きでして、気に入った言葉は必ずメモに残すようにしています。
受験生時代は、自分自身に向けた「税理士試験の必勝法」なるものもメモしていました(笑)
今回は、当時の言葉をそのまま一言一句いじらずにそのまま貼り付けてみたいと思います。
もともとは、自分に言い聞かすためにメモしていたものですので、他の方が読むとかなり意味の分からない部分も多いかと感じます。
その点は、囲い枠の部分で補足しています。
また、上から目線的な書きぶりになっておりますが、自分自身に言い聞かせるためのメモだったということでご容赦頂けると幸いです(滝汗)
自分自身に言い聞かせていた税理士試験必勝法~当時のメモを復元~
・ブログを活用しろ
受験生時代は自分のための記録としてブログを書いていました。意外にもブログを書くことで、自分自身の考え方の整理や、今後の決意表明といった感じで、受験勉強にもプラスの効果があったように感じます。
・自分の必勝パターンを作れ
・全ては予定表に落とし込め
受験専念時代には、1週間の時間割を事前に決めていて、毎日淡々と勉強を進めました。年内、年明け、GW、直前期といった時期ごとに、合格から逆算してどのようなことをやっておきたいかを踏まえて、時間割を設定していました。
・自習室へは一番乗り、最終退去が当たり前
「量より質」が大切なのは言うまでもありませんが、質を高めるためには量をこなすしかないと考えていました。会計士など他の資格を勉強されている方も含めて、一番最初に来て一番最後まで頑張って勉強しているような方は、結局のところ、しっかりと結果を残せていたように感じましたので、自分自身もそれに乗っかろうと考えていました。
・講師を活用しろ
自分自身でいくら考えても答えが出ないこともありますので、積極的に講師に相談するようにしていました。とはいえ、活用するなんていう言い方は言葉が悪いですね(汗)反省です(泣)
・質問は自分で仮定して回答を作ってから
講師に質問をするときは、事前に答えになると思われることを整理した上で質問をするように心がけていました。単に答えを確認するというよりは、答えにたどり着くための考え方のプロセスが間違っていないかを確認していたイメージです。
・理論暗記は一字一句やれ
初めから一字一句覚える気でいないと精度高く暗記が出来ないものだと感じていました。また、法律用語は一字変われば意味がガラッと変わりますので、その意味でも、一字一句覚えることを目指しました。
・ボールペンにこだわれ(字はきれいにかつ見やすく)
ボールペンにはとてもこだわりました(笑)あと、試験委員の方々はとても多くの答案を見るわけで、読みやすい答案の方が心象が良いだろうと考えていました。
・問題を解くスピードにこだわれ
早ければよいというものではありませんし、無駄に省略したり、ショートカットするのは逆に自分の首を絞めると考えていましたが、科目に対する理解が高まれば、自然と回答スピードも高まると考えていました。特に、簿記は全ての仕訳を問題用紙に省略せずきっちりと書いていましたが、解くスピードは速い方だったと記憶しています。
・簿記は仕訳命
「簿記は仕訳に始まり仕訳に終わる。」という名言を残した講師の方がいましたがとても共感していました。当時は仕訳にこだわって勉強するようにしました。
・受験科目を愛せ
恥ずかしいの一言です(苦笑)ただ、自分の受験する科目を好きになれなければ、もったいないなという気もします。好きなことは一日中考えられますが、嫌いだと勉強だと割り切らないといけません。法人税を勉強していたころは一日中法人税のことを考えていたような気がします。
・時間配分は絶対守れ
どんな問題が出ても、この時間が過ぎたら次の問題に行くと事前に時間配分を決めていました。どんな問題でも例外なくです。いつもと違うことをすると力を発揮できないということを簿記論の一年目の本試験で学びましたので、このマイルールは意識していました。
・100発100中を目指せ
法人税の受験専念時代の考え方になります。100回受験して50回受かる確率を、いかに51回にできるか、また、52回にもっていけるか。そして、最終的に以下に100に近づけれるかを考えていました。当時はどうしても法人税を一発で受かりたかったのだと思います(苦笑)
・専門学校の成績にこだわれ
専門学校の試験では、成績表優秀者の名前が掲示板に貼り出されますが、毎回自分の名前を載せることを意識していました。やっぱり、名前が載るとうれしいですし、載らないともっと頑張ろうと思えたので、いつもよい刺激になっていました。
・講師と仲良くなれ
受験のプロである講師の先生には本当に助けて頂きました。仲良くなれなんて言葉が悪すぎ(汗)ですが、教室講座を受講中の方は、講師の先生に頼ってみるのもありだと思います。
・質問電話を活用しろ
毎日、教室講座があるわけではありませんので、聞きたいときにいつも講師の先生がいるわけではありません。そんなときは、専門学校の質問電話を活用していました。これは本当にありがたい専門学校の制度でした。
・テンションが上がる音楽を作れ
どうやったら気持ちが乗ってくるのか。私の場合は、好きな音楽を聴くとテンションが上がり戦闘態勢に持っていくことが出来ました。本試験に関わらず、答練前なども音楽を聴いて気持ちを高めていました。
・貼り出された名前をモチベーションにしろ
あっ、重複していますね(汗)上記で書いた通りです・・・。
・理論は全部暗記しろ
専念受験だったからこその戦略でした。もし、働きながら受験するのであれば、その時の環境次第では違う戦略になるのかもしれません。
・教室受講は一番前の席に座れ
私にとっては、一番聞きやすいのは一番前。一番集中できるのも一番前。だから一番前に座ることが一番合格に近づくと考えていました。
・ライバルを作れ
教室講座のときは優秀な方を勝手にライバルにして、その方よりも良い点を取れるように気持ちを高めていました。WEB講座のときは、いつも成績表で上位にくる方を勝手にライバルにしていました。
・受験会場には下見に行け
本試験当日のハプニングだけは絶対避けたいと思っていましたので、受験した三回とも必ず事前に会場に下見に行きました。もちろん当日でないと中に入れませんので、施設の外までです。
・受験一月前は受験時間と同じ時間帯に答練を受けろ
本試験を想定して本試験と同じ時間帯で2時間の答練を受けるようにしていました。その時間帯で力を発揮できるために直前は毎日繰り返しました。
・情報は一元化しろ
あちこちに情報を分散すると効率が悪いですし、見落としの可能性もあるため、私自身はテキストに全て集約するようにしていました。
・間違いノートの究極は5つにまで絞り込め
間違いノートの項目が増えすぎてしまったので、絶対にやってしまいたくないものを5つに絞り込んで、試験前はその5つだけを頭に叩き込むようにしていました。
・間違いノートはエクセルで作れ
初めは手書きで作っていたのですが、項目ごとで絞り込んだり並び替えたりできないので、エクセルで作って印刷してテキストとかに貼り付けていました。
・答えに迷ったところは究極のお宝だ
専門学校の答練を受けていて、答えに迷ってしまったところというのは、自分の理解が足らないところなので、このような部分を見つけるために答練を活用していました。答えにたどりつく理屈が分からず、エイヤーで正解してしまったりした場合は要注意ですね。理解不足のままでスルーしてしまう可能性もあるため、問題用紙に大きく丸を付けておいて、正解か不正解かに関わらず、試験後にすぐに見返すようにしていました。
・自分が受からないはずがないと思い込め
メンタル強化のための暗示ですね(笑)もともと、ネガティブ思考なところがありましたので、自分に言い聞かせるようにしていました。
・体調管理はスポーツマン以上に気を遣え
例えば、プロ野球のピッチャーは利き手で重たいものを持たないとか、とにかく、生活の全てをその一点に照準を合わせて自分を管理しているわけで、その部分は見習いたいと思っていました。試験前は口に入れるものに気を付けたりとか、睡眠管理とか、とにかく、体調管理には気を付けました。
・毎日のリズムを崩すな
毎日の時間割を決めて、毎日一定のリズムでルーティンを刻むかの如く、淡々とこなすことに気を付けました。リズムが狂うと元に戻すのには時間がかかります。勉強のやりすぎにも気を付けました。
・GWは理論週間にうってつけ
GWは講義がありませんので、時間を有効に使うことができます。私自身は、毎年、GWを理論暗記週間にしてしまって、暗記の弱い理論を徹底的に覚えるようにしていました。
・テキスト命
法人税の勉強の頃は実務書を買ったりと、色々と浮気をしたのも事実ですが、最終的には、自分が通っている専門学校のテキストをきっちりやれば必ず合格できると感じるようになりました。
・答練は自分の思い込みをただすために受けろ
上記と被るところでもありますが、答練は自分の理解があやふやなところや、間違って思い込んでいたところをあぶりだすために活用していました。答練を受けてみて、このようなところが一つでも見つかれば、得した気分になっていました。
・コピー代をけちるな
専念受験生時代はかなりの極貧生活でしたが、そんな中で、絶対にケチらないようにしていたのが、答練のとき直しなどのコピーのための投資です。縮小したりすることなく、迷いなく普通にコピーするようにしていました。
・メモすべきは考え方の理屈
「なんでその制度があるのか」、「その制度ができた背景は何か」、「その計算式になるのはどういった理由からか」など、こういった理屈の部分を授業中に漏らさないようにメモしようと考えていました。個人的には、こういった背景をしっかり説明してくれる講師の先生に出会えてとてもラッキーでした。
まとめ
今回書かせて頂いたのは、「当時の自分自身にとって」必勝法だと思っていたものです。
当時の年齢や環境、自分の性格、目標などを踏まえたもので、誰しもに当てはまるものではないと考えますが、少しでも読んでいただいた方の参考になればうれしいです。
また、上から目線的な書きぶりですが、当時のメモのまま復元したということでご容赦頂ければと・・・(土下座)